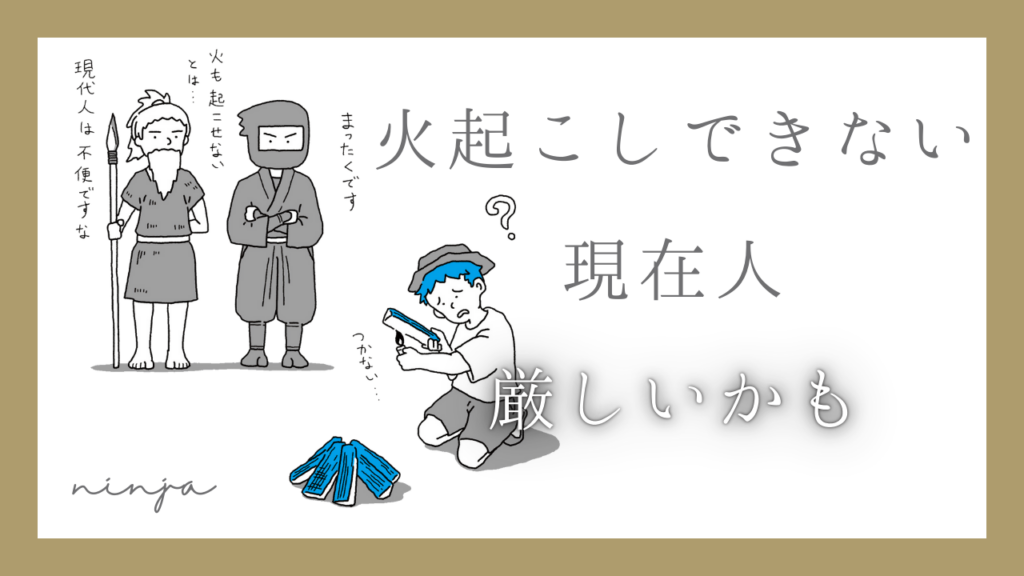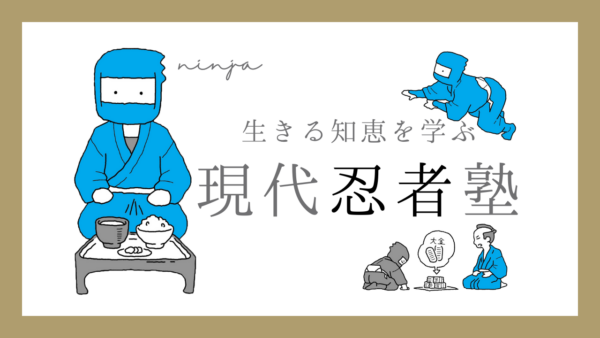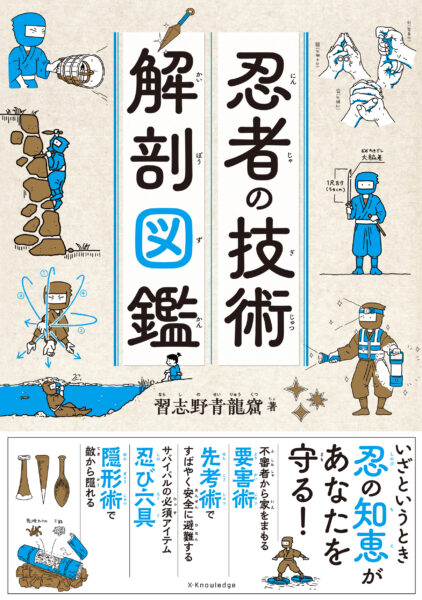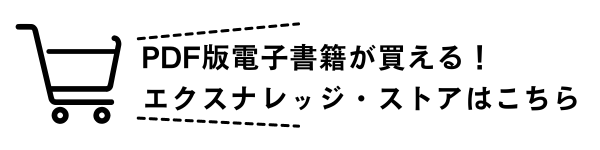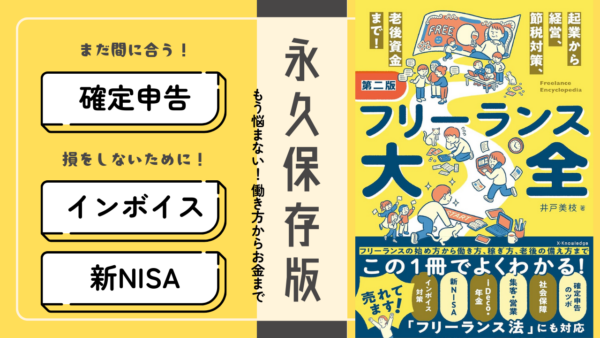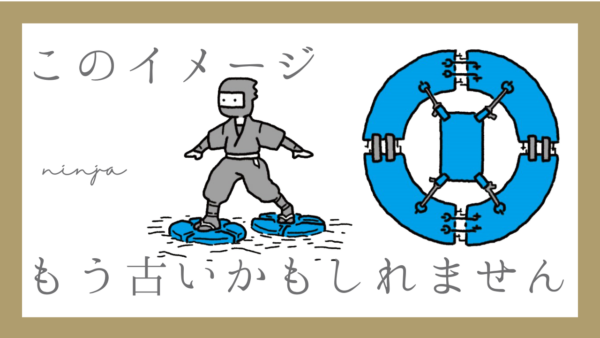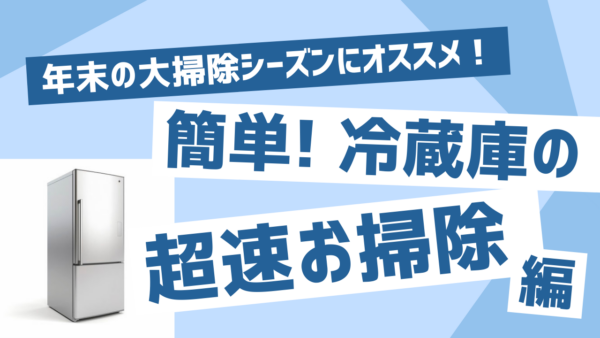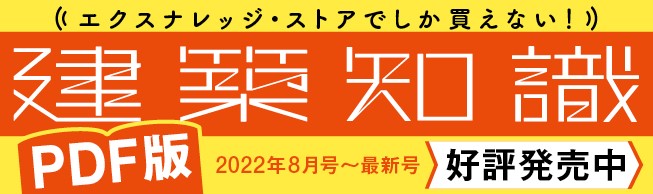忍者が使った火器の数々
剛盗提灯(がんどうちょうちん)
内部にジャイロ機構が組み込まれた提灯で、どの方向に向けても中の蝋燭が傾かないようになっています。
提灯を地面に伏せれば、火を消さずに闇に紛れることもできます。
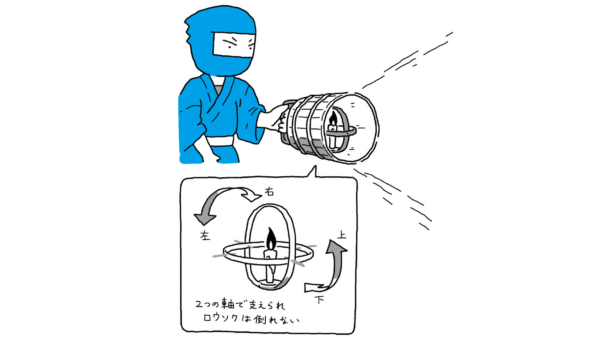
楯火炬(たてたいまつ)
楯と松明が一体化したもので、暗闇での戦闘に用います。
楯の上に覗き孔が開いていて、下に蝋燭を立てる台が付いています。
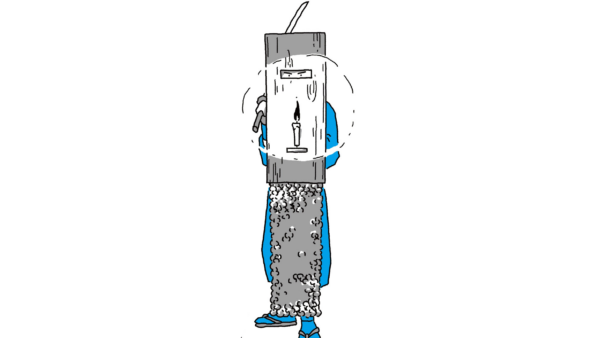
大きさは18×60㎝程度
焙烙火箭(ほうろくひや)
焙烙(茶やゴマを炒るための素焼きの土鍋)の中に火薬を詰めた爆弾です。
手投弾のような武器として使います。
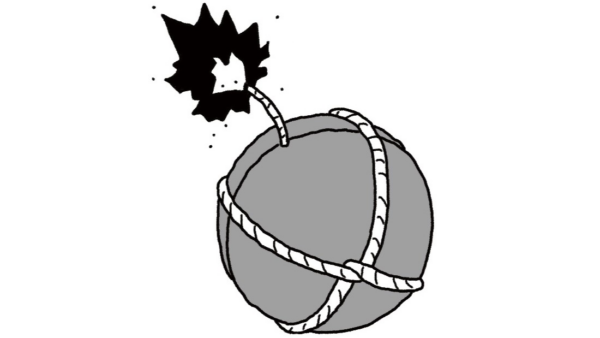
義経明松(よしつねたいまつ)
水牛の角を薄くくり抜いて、中に鳥の羽と水銀をいれて化学反応で光を出す照明器具です。

大国火矢(おおくにひや)
矢の先に火薬を入れた竹筒を取り付けて飛ばし、遠くから建物に火を点けられます。
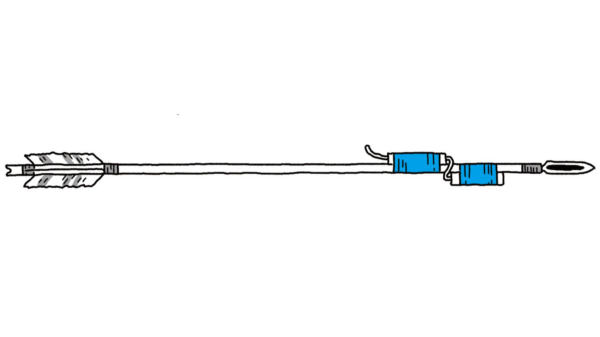
忍者は火種を持ち歩く
上記のような火器を使った火術を行うためには、着火道具を持ち歩く必要があります。
火の点いた炭や線香を香炉に入れたものや、予め火をつけた火縄などを火種にしていました。
忍者の火起こしグッズ「火箱」
火箱には、火起こしに必要な道具がすべて入っています。
大きさは10×10×5㎝程度です。
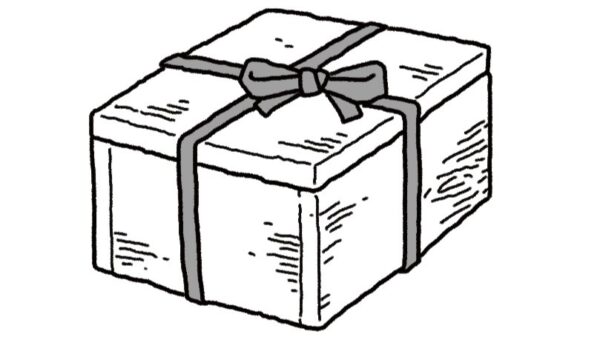
忍者の火おこし
火打石に、布や炭化させた綿などの「火口」を適量乗せて、火打金で勢いよく打ちます。
上手くいくと火口に火花が移り、小さな火が点きます。
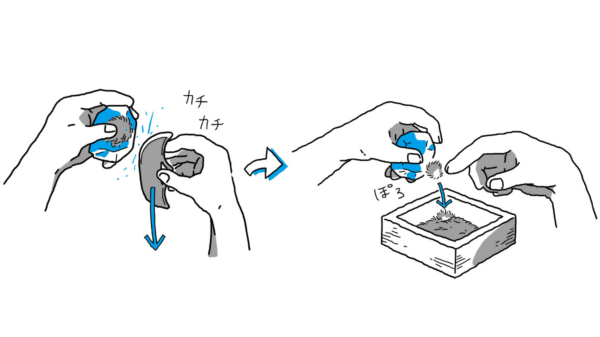
この火を附木に移してマッチ大の火にします。
優しく息を吹きかけながら火を移します。
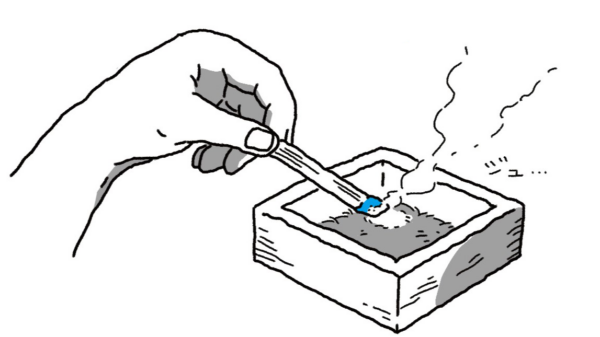
附木に火がついたら、その火を素早く蝋燭や小枝に移して、火起こし完了です。
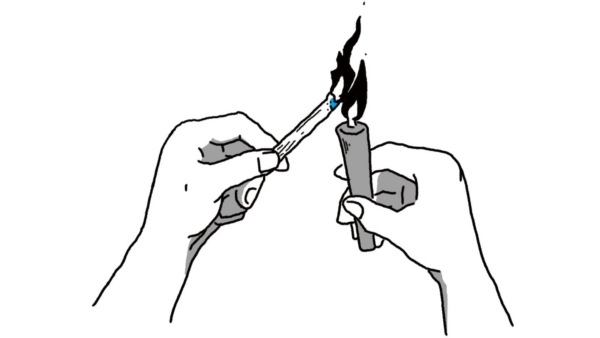
キャンプ道具で火おこしの修行
キャンプ用のメタルマッチを使って火起こしをしてみてください。
「打ち付ける」というより「こすり合わせる」ようにして火花を出します。
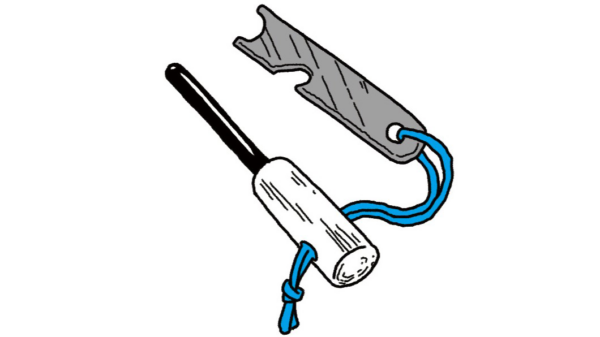
火花を大きくする火口は、チャークロスのほかに、植物の綿毛、衣服の綿、埃を集めたものなども使えます。
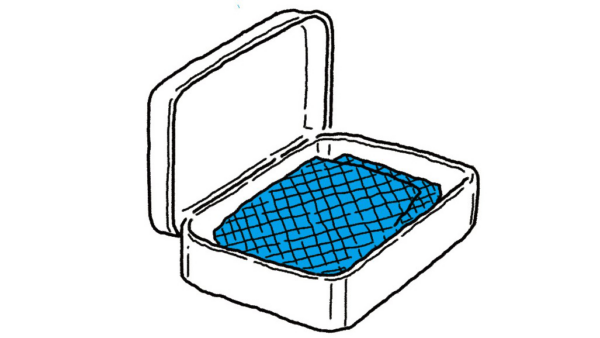
附木には、薄い杉の板に硫黄を塗ったものや、フェザースティックなどを活用してください。
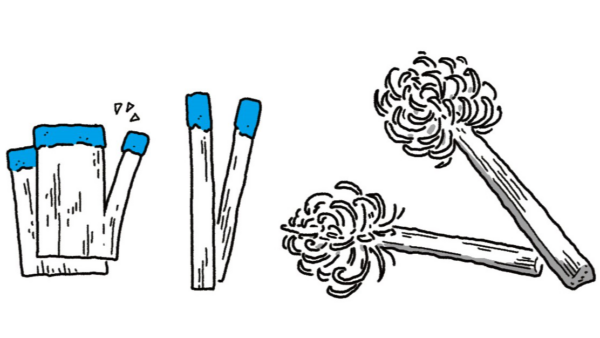
火起こしの稽古は、キャンプ場などの安全な場所で、後始末や火傷に十分に注意して行いましょう
『現代忍者塾』連載一覧へ
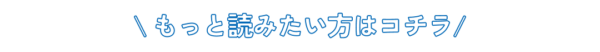
定価 1,700円+税
ページ数 144
判型 A5判
発行年月 2025/07
ISBN 9784767834368
解説
習志野青龍窟(ならしの・せいりゅうくつ)
忍道家。武術家。松聲館技法研究員。港区防災アドバイザー。各種イベントや国内外のメディアに多数出演。映画の忍術指導も担当。山修行や断食の実践、稽古、国際忍者学会への参加など精力的に活動している。今に役立つ温故知新の心身運用法を指導している。小学校や大学などでセミナーや教室なども開催している。
X(旧Twitter)アカウント:習志野青龍窟 忍道家(@3618Tekubi)
YouTube:忍道家 習志野修行チャンネル
イラスト
齊藤きよし(さいとう・きよし)
忍術研究家。デザイナー。イラストレーター。パルクール講師。桑沢デザイン研究所卒業後、某自動車企業勤務を経て独立し、現在は「Shinobi Design Project」を立ち上げ活動。自ら古典的な忍術を研究・修行・実践し、現代の仕事や暮らしに活かせる生きた忍術を探求。学校等で忍術を活かした体験・実践的な情報教育の指導も行う。著書に『図解 万川集海』。「SDP STORE」にて忍器・忍具の製作と販売も行う。
X(旧Twitter)アカウント:きよし|デザインと忍者とパルクール(@Kiyoshi_Design)
公式ホームページ:Shinobi Design Project