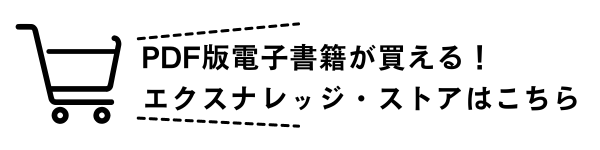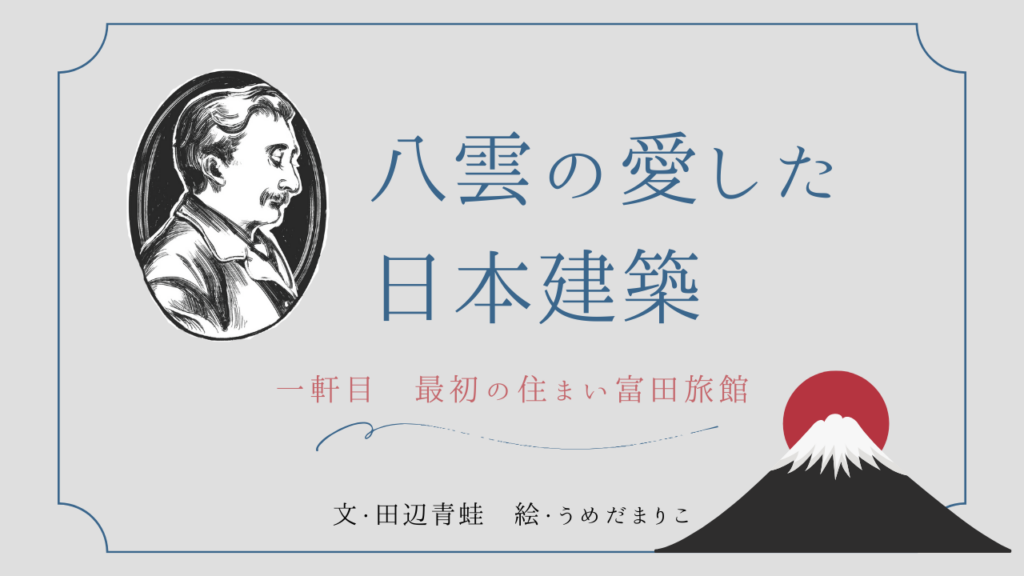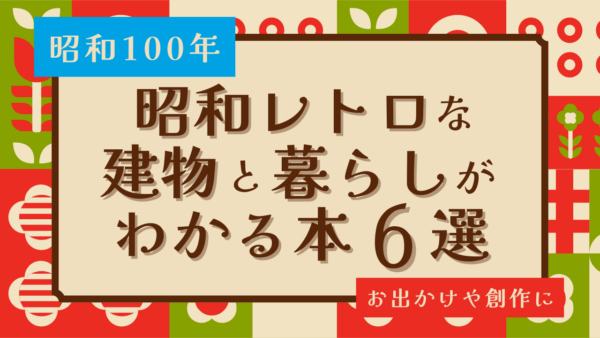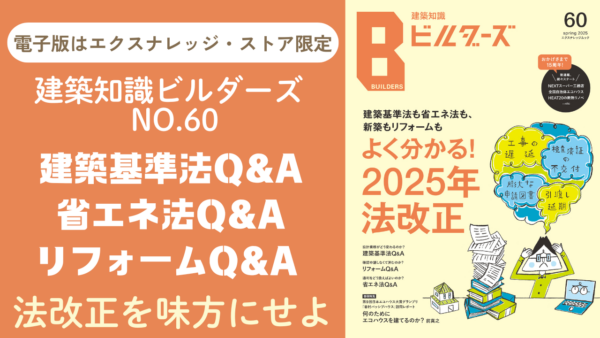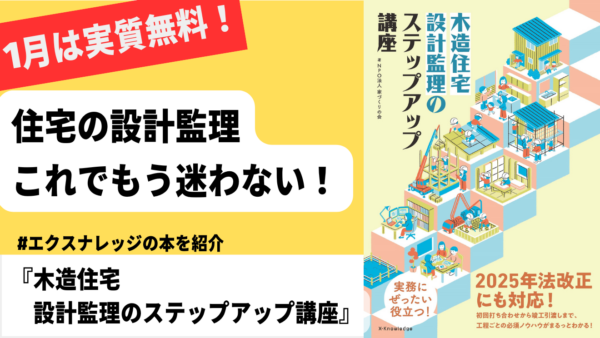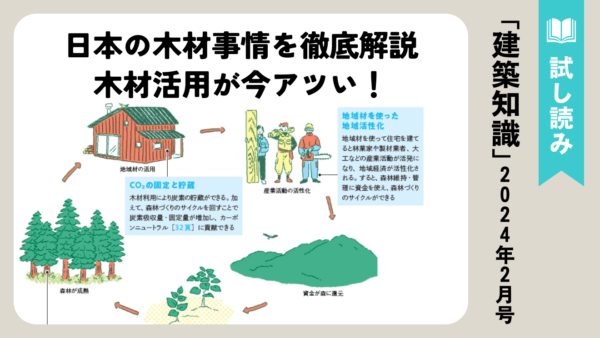連載「八雲の愛した日本建築」は「建築知識」2025年11月号から連載中!
一軒目 最初の住まい 富田旅館

松江に着いた八雲が最初に泊まった宿。建物は現存せず、現在は大橋館という旅館が建っている。 場所:島根県松江市末次本町40
日本では、『怪談』などの著書で知られる小泉八雲(出生名・パトリック・ラフカディオ・ハーン)は、1850年6月27日にギリシャ西部のレフカダ島に生まれた。
その後、2歳の時にアイルランドに移り両親は離婚。父方の大叔母サラ・ブレナンに養育されるが、16歳の時、遊戯中の事故で左目を失明してしまう。19歳の時、養母のサラが破産したことから、進学を諦めアメリカへ渡航。
食べるものや眠る場所にも事欠くような赤貧の生活を体験した後、印刷所の手伝いを経てジャーナリストになり、文芸評論から事件報道、翻訳、小説の執筆まで手掛けた。
それから、ルイジアナ州ニューオーリンズ、カリブ海のフランス領マルティニーク島へ移り住んだ後、39歳の時に来日を決意。1890年4月にハーパー社の記者として横浜に来た後、記者を辞め、教師として松江にやって来た。
そんな八雲が日本で過ごした期間の住まいと愛着のある建物について、この連載では紹介していく予定だ。
1890年7月、島根県尋常中学校(現島根県立松江北高等学校)及び、島根尋常師範学校(現島根大学教育学部)に英語教師として赴任することが決まった八雲は、姫路から人力車で津山、勝山、犬挟【いぬばさり】峠を越え、関金【せきがね】、下市【しもいち】へ行き、それから米子で蒸気船に乗り換え、中海と大橋川を渡り8月30日の夕方に松江に到着した。
 松江では、島根県の毛利八弥【もうりはちや】事務官が埠頭で出迎えてくれた。彼はラストネームの「Hearn」を「ヘルン」と書類に記載し、それ以来、松江の人たちから「ヘルン先生」と呼ばれるようになり、本人もその響きが気に入ったことから日本での愛称となった。八雲は、桟橋の対岸にある富田旅館に落ち着くと、勤務先の島根県尋常中学校の教頭、西田千太郎【にしだせんたろう】の訪問を受け、彼の素朴で親切な人柄にすっかり魅了された。西田が病で若くして亡くなるまで、西田と八雲は親友の仲だった。
松江では、島根県の毛利八弥【もうりはちや】事務官が埠頭で出迎えてくれた。彼はラストネームの「Hearn」を「ヘルン」と書類に記載し、それ以来、松江の人たちから「ヘルン先生」と呼ばれるようになり、本人もその響きが気に入ったことから日本での愛称となった。八雲は、桟橋の対岸にある富田旅館に落ち着くと、勤務先の島根県尋常中学校の教頭、西田千太郎【にしだせんたろう】の訪問を受け、彼の素朴で親切な人柄にすっかり魅了された。西田が病で若くして亡くなるまで、西田と八雲は親友の仲だった。
八雲が1894年に出版した『知られざる日本の面影』の中の「神々の国の首都」で、松江で迎える朝の様子をこう書いている。
〈松江の朝の最初の音は、まるで巨大でゆっくりとした脈動が、眠っている者の耳のすぐ下で打ち鳴らされているかのように響いてくる。それは大きく、やわらかで、鈍い衝撃音――まるで心臓の鼓動のように規則正しく、くぐもった深みをもち、枕を通して震えが伝わってくるため、聞くというよりも感じる音だ。それは、米搗(こめつき)の大きな杵(きね)の音である。米搗とは米を精白する職人で、柄の長さが十五フィート(約4.5メートル)ほどもある巨大な木製の横杵を、支点で水平に釣り合わせた道具を使う。柄の端に全身の体重をかけて踏み込むと、反対側の杵が持ち上がり、そのまま自重で米桶の中に落下する。その規則的でくぐもった反響音は、私には日本の生活音の中で最も物悲しく感じられる。それはまさに「この国の脈動」そのものだ。
やがて、禅宗の東光寺の大鐘が町中に鳴り響き、続いて、私の家の近く、材木町にある小さな地蔵堂から、朝の勤行を告げる太鼓の物悲しい響きが伝わってくる。そして最後に、最も早い行商人たちの声が響き始める――「だいこやい! かぶやー、かぶ!」―― これは大根やその他の珍しい野菜を売る者たちの声。「もややー、もや!」――これは、炭火を起こすための薄い焚き付けの小片を売る女たちの、哀調を帯びた呼び声である。〉(原文『Glimpes of Unfamiliar Japan』by Lafcadio Hearn(1894) より、田辺青蛙が翻訳)
そういった物音で目を覚ました八雲は、宿の2階の部屋の障子を開け放ち、宍道湖の様子を眺めた。淡い夢のような色彩と霞の中から浮かび上がる、蜆【しじみ】取りの船、嫁が島の影。
この風景を見て、八雲は心地よさを感じた。
八雲は朝に牛乳を飲み、富田旅館の女中、お信【のぶ】に「エッグ・フーフー!」(たまごの、ふーふーするくらい熱いの)と言って何度も目玉焼きを頼んでいたそうだ。
糸コンニャクの煮物を八雲は気持ち悪い虫に似ているとして非常に嫌い、昼と夜には燗をした日本酒を1合飲み、レモネードに似た色合いだけれど味はシェリー酒に似ていると評した。白ごはんは苦手だったので、巻きずしを代わりに食べていた。
他にも黄金牡丹という卵黄をたっぷり使った和菓子や、白いんげんの羊羹を好んでよく食べた。

新天地松江で、そんな風に生活を楽しんでいた八雲だが、冬には、すっかり参ってしまった。大寒波到来で、宍道湖の湖面はカチコチに凍り付き、雪もひざ丈まで積もるほどの厳しい寒さ。その影響で体調を崩し、八雲は酷い気管支炎にかかってしまった。
学校の授業も休んで、療養中だった八雲のところにお信の紹介でセツという武家の娘が住み込みでやって来た。
それが、後の伴侶となる小泉セツとの出会いだった。
八雲の世話をするためにやってきたセツは、言葉はあまり通じなかった。が、上手くいかなかった最初の結婚や、困難を通過してきた人生、そして怪談好きであったことなど、互いの境遇や好みが似ていることもあってか、2人はしだいに惹かれあい、自然と夫婦同然の関係となっていった。だが、当時は世間からは洋妾(ラシャメン、外国人相手の妾)と陰口をたたく人もあったそうだ。
セツにまつわる知られたエピソードで、八重垣【やえがき】神社の鏡池で行った縁占いがある。
社の森にある鏡池の水面に、薄紙で作った舟に硬貨を1枚載せ、セツと2人の女友達はおそるおそる、水面に船を浮かべ様子を見守った。この船がどこで沈むかによって縁が分かるという占いだったからだ。
2人の女友だちの船は、すぐ水中に沈んでしまった。だが、セツの船だけが遠くまで運ばれてしまい、池の端の方まで行ってようやく沈んだ。なので、もしかしたらセツはとても遠くの人と縁があるのではと思ったそうだ。実際、2人の女友だちは近所の男性と縁付いて、結婚した。
八重垣神社は、素盞嗚尊【すさのおのみこと】がヤマタノオロチを退治し、奇稲田姫命【くしなだひめのみこと】を救い、夫婦になったという伝説が残る場所で、今でも良縁を願う人々から厚い信仰を集めている。
セツの書いた『思い出の記』に、当時の出会いと八雲の暮らしぶりについて書かれた部分がある。
〈ヘルンが日本に参りましたのは、明治二十三年の春でございました。ついて間もなく会社との関係を絶ったのですから、遠い外国で便り少い独りぽっちとなって一時は随分困ったろうと思われます。出雲の学校へ赴任する事になりましたのは、出雲が日本で極古い国で、色々神代の面影が残って居るだろうと考えて、辺鄙【へんぴ】で不便なのをも心にかけず、俸給も独り身の事であるから沢山は要らないから、赴任したようでした。(中略)私の参りました頃には、一脚のテーブルと一個の椅子と、少しの書物と、一着の洋服と、一かさねの日本服位の物しかございませんでした。
学校から帰ると直に日本服に着換え、座蒲団に坐って煙草を吸いました。食事は日本料理で、日本人のように箸で食べていました。何事も日本風を好みまして、万事日本風に日本風にと近づいて参りました。西洋風は嫌いでした。西洋風となるとさも賤しんだように『日本に、こんなに美しい心あります、なぜ、西洋の真似をしますか』と云う調子でした。これは面白い、美しいとなると、もう夢中になるのでございます。〉(『思い出の記』小泉セツ) ※
やがて夫婦同然となった八雲とセツの2人は、手狭になった大橋川沿いの住まいであった織原家借家から、松江城北の武家屋敷(現・小泉八雲旧居)に引っ越した。
小泉八雲の作品にセツの語りは必要不可欠だった。なので、富田旅館のお信を通じてセツと八雲が出会っていなければ、今も読み継がれている名著『怪談』は誕生していなかったかも知れない。
セツが初めて八雲に語った怪談は「鳥取の布団」という話だった。この話を聞いた八雲は、セツに「あなた、私の手伝いできる人です」と伝え、とても喜んでいたそうだ。
折角なので「鳥取の布団」の要約をここに掲載しよう。
〈淋しそうな夜、ランプの心を下げて怪談を致しました。ヘルンは私に物を聞くにも、その時には殊に声を低くして息を殺して恐ろしそうにして、私の話を聞いて居るのです。その聞いて居る風が又如何にも恐ろしくてならぬ様子ですから、自然と私の話にも力がこもるのです。〉
(『思い出の記』小泉セツ)※
とあったので、できればこの物語の部分は、薄暗い部屋で読んで欲しい。
「鳥取の布団」
鳥取にある、とある真新しい宿に商人が泊まった。 疲れ果てて眠っていると、彼は真夜中に布団から聞こえる小さな子供の声で起こされた。
「兄さん、寒かろう?」
「おまえ、寒かろう?」
客は最初、別の部屋に泊まっている子供のいたずらか何かだろうと思ったが、そうではなかった。声は布団から聞こえていたからだ。
客は、こんな宿泊まっていられるかと、苦情を宿の主に伝えて出て行った。その後も何度かそんなことがあったので、気になった宿の主は実際に布団で眠ってみた。
すると、やはり布団から声が聞こえてきたのであった。
宿の主は布団の元の持ち主を探して、古道具屋を訪ねた。
元の布団の主は、2人の小さな男の子がいる貧しい家庭だということが分かった。2人の子は親を亡くし、家財道具を売り払って生活していた。ただ最後に売る物が無くなり、最後に2人に残されたのは布団1枚だけだった。それすらも、家賃代わりにと大家に取り立てられ、2人は寒い日に外に追い出されてしまった。
外は雪も降り始め、2人は身を寄せ合い震えるしかなく、やがて雪は積もり、2人の体を雪で出来た布団のように覆っていった。
翌朝、2人は雪の中で互いに抱き合った姿で亡くなっていた。
この話を聞いた宿の主は、布団を寺に寄贈し、哀れな兄弟の霊を慰めるために僧侶に読経を頼んだ。それ以来、布団は何も言わなくなったそうだ。

八雲に怪談を語り聞かせたセツは、まさに優れた語り部であった。
この話を聞いた時の松江は1週間続く吹雪に見舞われていたそうで、西田氏も「寒威、積雪共に近年稀有なり」と日記に記している。
八雲自身も『古事記』の英訳などで知られるチェンバレンに、このような冬が2〜3回続いたら生きていられないだろうという内容の手紙を送っている。
うす暗闇の中で、寒さの中に放り出された兄弟の話を聞いた八雲は一体どんな心地だったのだろうか……。
富田旅館は昭和6年の末次町大火で消失し、その後新築されたが現在は大橋館に売却されて、石碑しか残っていない。
ちなみにこの大橋館の主人は外国人で、後に女将となる女性とハワイで出会い結婚して、旅館の若旦那となった。八雲とセツをつなぐ切っ掛けとなった旅館の主が国際結婚というのも不思議な縁を感じる。
※『思い出の記』(小泉セツ)の出典:青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/)より
底本:「小泉八雲全集 別冊」第一書房(1927年12月発行)
最新号「建築知識」2025年12月号では「二軒目 小泉八雲旧居」が掲載されています。どうぞ今後もご贔屓に!

建築知識2025年12月号 最新研究でよみがえる!古代ギリシアの建物と暮らし図鑑
定価 1,800円+税
判型 B5判
著者プロフィール
文・田辺青蛙(たなべ せいあ)
『生き屏風』で日本ホラー小説大賞短編賞を受賞。著書に「大阪怪談」シリーズ、『関西怪談』『北海道怪談』『紀州怪談』『魂追い』『皐月鬼』『あめだま 青蛙モノノケ語り』『モルテンおいしいです^q^』『人魚の石』など。共著に「京都怪談」「てのひら怪談」「恐怖通信 鳥肌ゾーン」各シリーズ、『怪しき我が家』『読書で離婚を考えた』など。主宰イベント「蛙・怪談ガタリ」はじめ、怪談イベントにも出演多数。
絵・うめだまりこ
東京生まれ。英国・米国・日本でイラストレーター・絵本挿画家・漫画家として活動。ゲーム、絵本、映像作品など多岐にわたりアートを提供。著作に『渡英2年うめだまのイギリス自由帳』『流転7年うめだまのイギリス・アメリカ自由帳』(ともにKADOKAWA)、『Moon andMe :The Little Seed』(挿絵/Scholastic)
「建築知識」連載試し読みはほかにも!
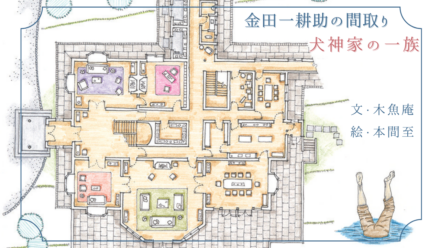
「金田一耕助の間取り」犬神家の一族
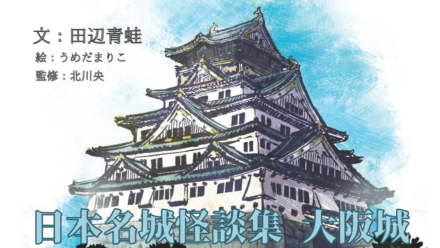
「日本名城怪談集」大坂城に数多く伝わる怪談とは?
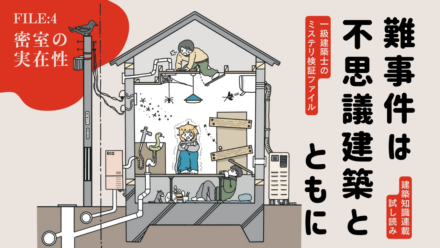
「難事件は不思議建築とともに」実際の建築に”密室”は存在するか?