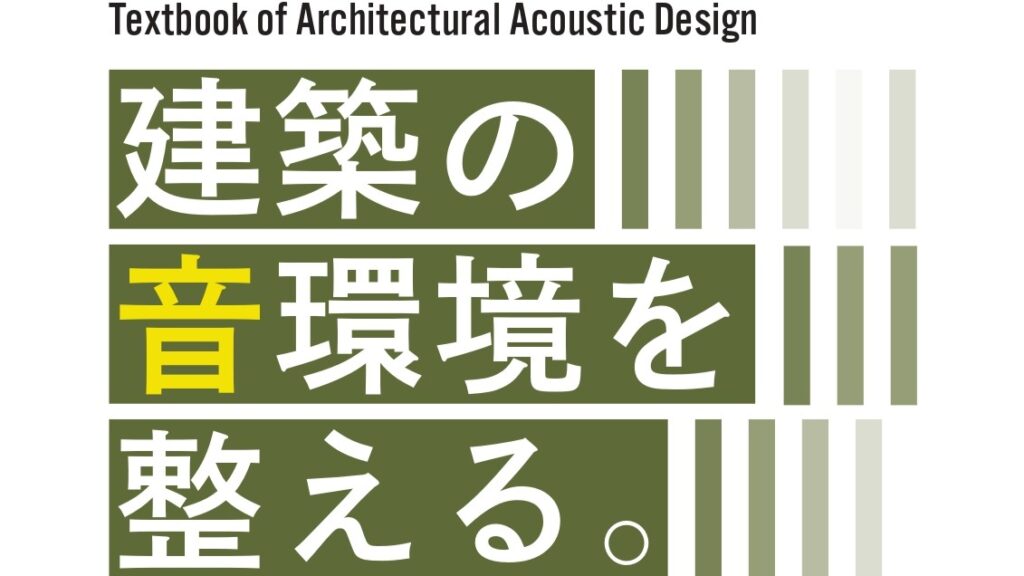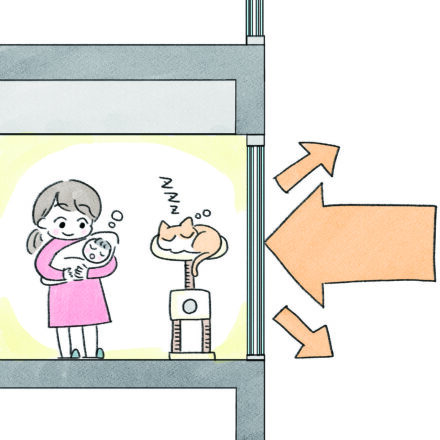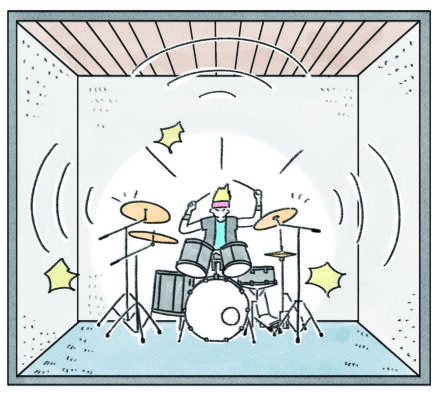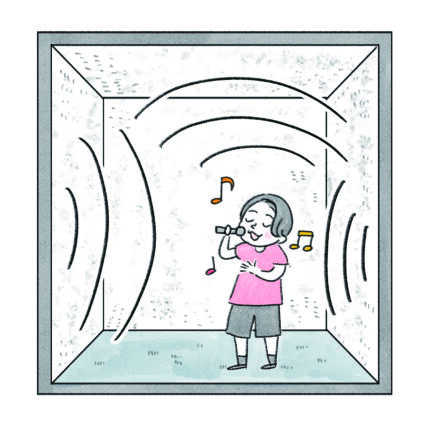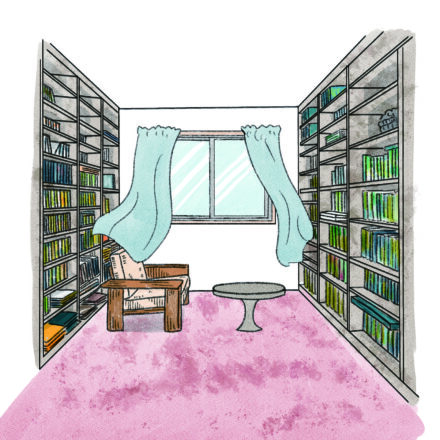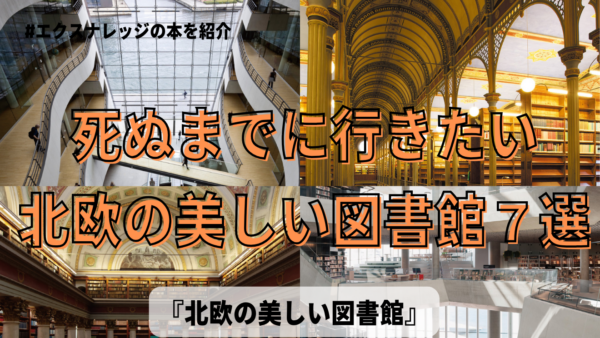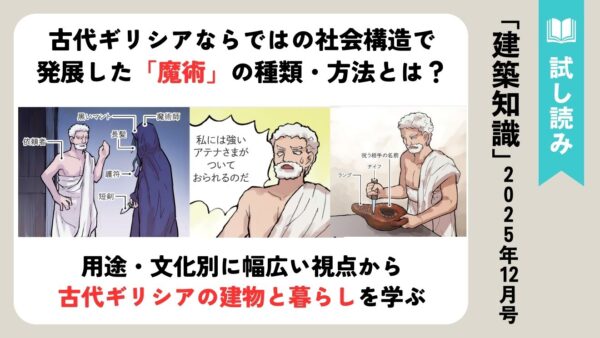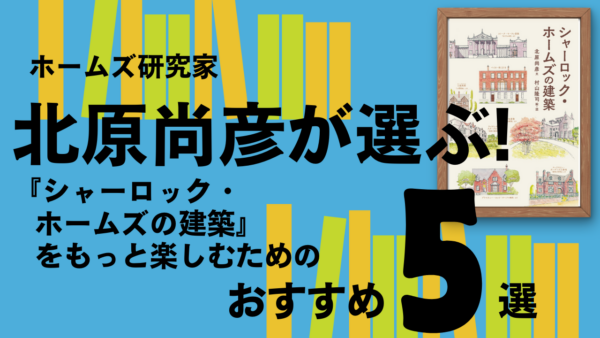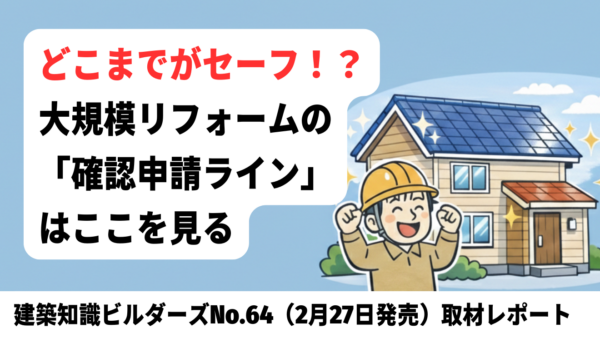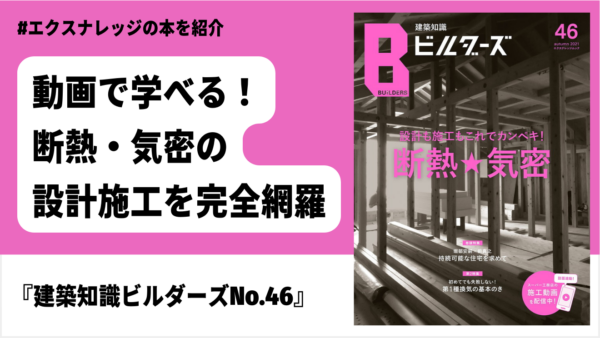1 吸音と遮音の違いを正しく理解する
暮らしのなかで「防音」という言葉を耳にすることがよくあります。防音室や防音ドア、防音シートといった製品名にも使われています。「防音」は一般的に、音を漏らさない・侵入させないための対策全般を指します。しかし、音響設計の分野では防音ではなく、「吸音」と「遮音」という語を用います。
それぞれを正しく理解して使い分けることが重要です。「防音」の効果を得たい場合は、まず「遮音」の効果を確保することが基本です。ただし、室内で発生した音を外へ漏らさないように「防音」するのであれば、発生音を低減するための室内での「吸音」が有効です。また、「吸音」には外部から入ってきた音を低減し、「防音」の性能を高める効果もあります。
A 遮音―音を“遮る”ことで伝えない
「遮音」とは、音を空間の外へ出さない、または外部から内部へ入れないようにすることです。壁やドア・サッシ、床などを遮音構造とすることで音の通り道を物理的に遮り、音漏れや外部からの騒音侵入を防ぎます。吸音が室内の音響環境を整えるのに対し、遮音は空間の音のやり取りを遮断することに主眼があります。
目的
▶ 外部からの騒音(例:車の走行音・隣家の生活音など)を遮断
▶ 室内の音(例:音楽・会話・足音[※1])を屋外や隣接する空間に漏らさない
▶ 隣室への音の干渉を減らす
遮音によく使われる材料
重量のある建材:コンクリート壁・コンクリートスラブ、乾式遮音壁構造など
建具の遮音化:防音ドア、気密性の高い2重サッシ[※2]
特殊構造:浮床構造、防振遮音構造(BOXinBOX)など
B 吸音―音を“吸収”して反響を抑える
「吸音」とは、室内で発生した音が壁面や天井面にぶつかった際、その面が音を反射せず“吸い込む”ことです。吸音作用の多くは、壁・天井表面の材料が音のエネルギーを熱エネルギーなどに変換し減衰させることにより得られますが、面と面の隙間から音が漏れたり、音エネルギーがそのまま面を透過するものも含まれます。吸音により室内の音量は低減し、反響(残響)や音のこもりも抑制。喧噪感を抑えたり、音の明瞭さを確保したりするうえで欠かないものです。
目的
▶ 室内の音量、喧噪感などを適正にする(例:駅・食堂・ロビーなど)
▶ 会話音声などの明瞭度を高める(例:会議室・教室・講堂など)
▶ 音の反射をコントロールし、場の用途にふさわしい快適な音環境をつくる
吸音によく使われる材料
多孔質吸音材:多数の微細な孔や連続した気泡をもつ素材。グラスウールやロックウール・ロックウール化粧吸音板などが代表的
軟らかな仕上げ材:カーペット・カーテンなど
複合構造:有孔板、パンチングメタル、木リブなどの保護材と多孔質吸音材の組み合わせなど
※1 室内で発生する音は、空気中に発せられた音が壁や床を透過して伝わる「空気伝搬音」と、振動を建物に直接加え、その振動が建物を伝わった先で音として放射される「固体伝搬音」とがある。壁越しの会話は「空気伝搬音」、上階の足音は「固体伝搬音」
※2 安定した遮音性能を求める場合には2重サッシが有効。それぞれ独立した枠に納めた気密性の高いサッシを2重に設け、サッシの間には空気層を設ける。ガラスには厚みに応じて遮音性能が低下する特定の周波数帯が存在するため、2重サッシでは一般的に2枚のガラスの厚みに2倍以上の差を設けると効果的である。複層ガラスはガラス厚の組み合わせや構造によっては特定の周波数帯で音が透過しやすくなる「共鳴透過現象」が生じることがあるので注意が必要
2 音が響きやすい建築の特徴
室内で音が過剰に反響すると、うるささや会話の聞き取りづらさを感じるだけでなく、集中力の低下、さらには心理的ストレスにもつながります。近年の建築では、仕上げ材や空間構成の変化に起因して音が反響しやすくなっており、残響過多になる傾向。ここでは、建築空間で残響過多が生じる主な3つの要因を紹介します。
A 空間の大きさ―容積が大きいほど残響が長くなりやすい
音は、壁や天井にぶつかって跳ね返り、耳に届きます。天井が高い、スパンが大きいなど容積の大きな空間では、音が高い天井や遠い壁に反射して戻るまでに時間がかかることなどから、残響が長くなります。
対策のポイント
▶天井が高く容積が大きい空間、さらにはそこで会話や音声による情報伝達などが用途として見込まれる空間では、天井や壁などに吸音材を設置する
B 仕上げ材の硬さ―硬い素材ほど音を跳ね返す
仕上げ材の素材は、室内の音環境に直接影響します。石膏ボード、ガラス、フローリング、コンクリートなどの硬質な材料は音をよく反射する素材であり、室内で発生した音を吸収しません。一方、畳や織物などの軟らかい素材には音を吸収する性質があります。近年は昔の建築に比べより硬い素材が好まれるようになったこと、建築物の高気密・高断熱化が進み音が外部へ漏れる隙間が少なくなったことも、音の反響を助長する要因になっています。
対策のポイント
▶音を吸収しやすい軟らかい素材や吸音仕上げ材を取り入れてみる
▶床や壁の一部をカーペット、布製パネルなど吸音性のある仕上げに変更する
C 物の量―“何もない”が音を響かせる
家具やカーテン、ラグといった“モノ”の存在も、音の吸収や拡散に一定の効果をもっています。ミニマルデザインの空間や、引越し直後で家具がまだ少ない部屋では、音の反響が強まり、声や生活音が不快に響くことがあります。
対策のポイント
▶布製ソファ、ラグ、カーテンなどの布製素材を配置する
▶本棚なども音の拡散や吸音に多少の効果があるため、適度に取り入れる
NOTE 覚えておきたい音の指標
① 吸音率とNRC(Noise Reduction Coefficient)
吸音率は、入射してきた音エネルギーを材料や仕上げ面がどれくらいの割合で吸収するかを示す比率(0.00~1.00の数値)。1に近いほど吸音性能が高いことを示します。窓が開放されているとき、窓に入射してきた音エネルギーは戻らないので、吸音率は1になります。吸音材料を選ぶ際にはこの値を確認します。周波数によって値が異なるので、吸音率は周波数ごとに示されます。一般的な発生音で多い帯域である4つの周波数帯域(250Hz・500Hz・1,000Hz・2,000Hz)の吸音率を平均したNRCという値も最近はカタログに載ることが多くなっています。簡易に性能を比較するにはNRCの値を参考にするのも便利。
② 音響透過損失とTLD
音響透過損失は、音が建材などを透過する際にどれだけ減衰するかを示す遮音の指標です。材料や遮音構造などの遮音性能を単位面積当たりの数値で評価するために使われます。単位はデシベル(dB)で表されます。周波数ごとに示され、数字が大きいほど遮音性能が高いことを示します。一方、TLDは音響透過損失を周波数ごとの評価曲線に当てはめて、1つの数値で部材の遮音性能を示す指標です。乾式遮音壁などのカタログなどではTLD値で性能を表示するケースも多くあります。ただし、いずれの値も部材の性能であり、室間の遮音性能を示すものではありません。
③ 音圧レベルと騒音レベル
単位はどちらもdB(デシベル)。音は気圧の変化であり、その変化の大気圧からの差分が音圧です。さらに、対数尺度を用いて表したのが音圧レベル。騒音レベルは、聴覚の特性を考慮した感覚的な音の大きさを表すために、人の音の大きさに対する感受性(低い音に感度が低い)を模擬した特性(A特性)で音圧レベルを重み付けした指標。環境基準や騒音規制法などには、騒音レベルが用いられます。
④ 残響時間
室の響きの長さを示す指標です。室内で音を発生させ、十分に空間を満たした後、音を止めて60dB減衰するまでに要する時間が残響時間です。単位はs(秒)。室の容積に比例し、室内の吸音力(正式には等価吸音面積)に反比例します。一般的に残響時間が短いほど音がクリアに聞こえやすいことを示します。推奨値は室の大きさに応じて異なりますが、クラシックコンサート会場などでは長い響きが好まれ、スピーチを行う会場などでは短い響きが好まれる傾向があります。